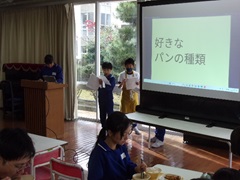1月21日(水)、5年生家庭科のミシンの学習に、地域ボランティア6名の皆さんがお手伝いに来てくださいました。
ボランティアの皆さんには6つの班にそれぞれ一人ずつついていただき、子供たちの学習の様子を見守りながら、細かい実技指導をしていただきました。日頃、学級担任一人ではなかなか目が行き届かないところも、丁寧に見ていただき、学習が大変スムーズに進みました。地域ボランティアの皆さん、ありがとうございました。
今後もミシンの学習の際には、地域ボランティアの皆さんのお力をお借りすることになっています。よろしくお願いします。